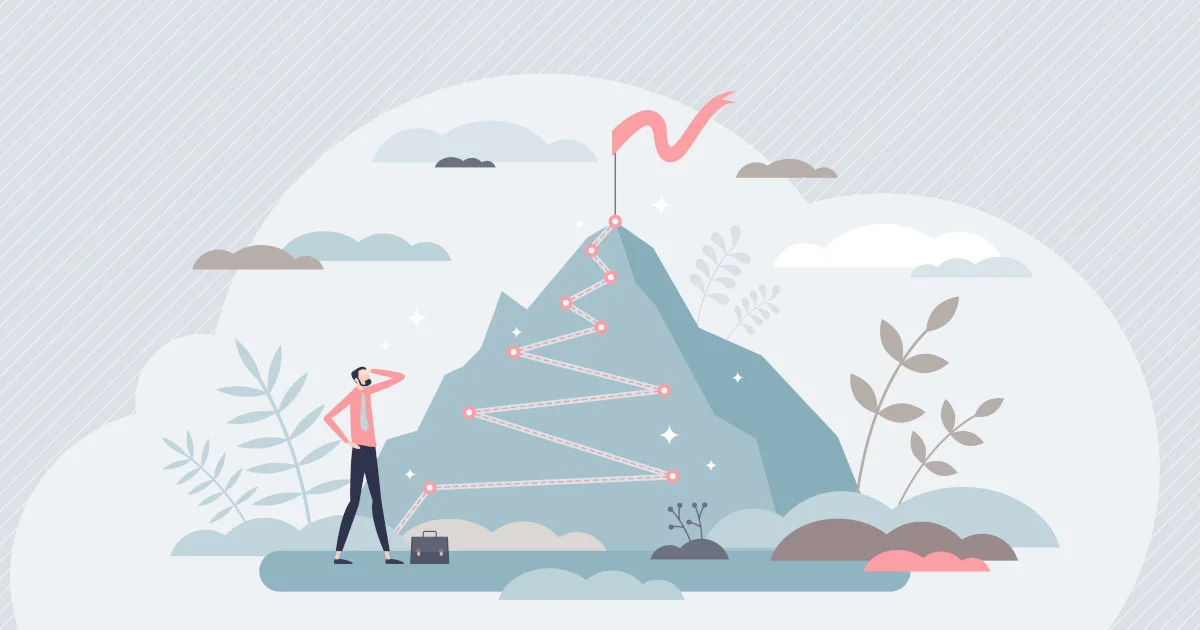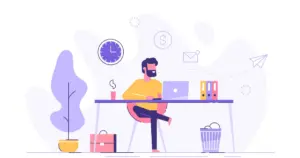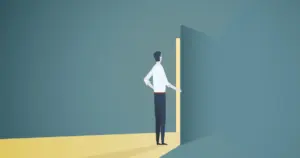「いつになったら開発をやらせてもらえるんだろう…」 SESで働くITエンジニアにとって、これは決して珍しい悩みではありません。現場によっては雑務やテスト比率が高く、案件待機が続くこともあります。そうなると、時間は積み上がるのに“開発経験”は増えないというジレンマに陥りがちです。
本記事では、なぜSES環境で開発経験が蓄積されにくいのかを構造的に整理し、その停滞を解消する実行可能な解決策を“再現性・費用対効果・リスク”の観点で紹介しています。さらに、よくある失敗パターンをケーススタディ化し、是正アクションと効果指標を解説しています。
この記事を読み終えたあとに、選択肢が少しでも広がり、ほんの少しでも前進するお手伝いができたならうれしいです。
- 開発タスクがほとんど回ってこず、監視や事務作業が中心になっている
- テストや資料作成ばかりで、コードレビューや設計議論に参加できない
- 案件待機が長引いており、履歴書に空白期間が増えそうで不安
- 希望言語や業務領域と配属がズレているが、打開策が見えない
- 自社開発や社内SEなど、別のキャリアへ移るべきか迷っている
SESエンジニアが開発経験を積めない現状
1) SES業界の仕組みと契約形態
SESは「準委任契約」に基づき、客先に常駐して業務を行う形態が中心です。 特徴的な側面として、いわゆる“案件ガチャ”(現場ガチャ)が挙げられ、配属先や契約条件によって、成長できるかどうかが大きく変わります。
| 区分 | 内容 | 依頼側の期待 | 関与領域 | 成長のしやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 準委任(SES) | 時間や労力を提供 | 柔軟な稼働・不足補充 | 運用〜開発の一部 | 現場により差が大きい |
| 派遣 | 指揮命令を受ける形態 | 定型業務の安定稼働 | 保守・運用・事務寄り | 限定的 |
| 請負 | 完成責任を負う | 成果物の納品 | 要件〜リリース | 一貫経験で伸びやすい |
- 契約形態によって、関われる作業範囲と責任が違う
- 「SESだから全部ダメ」ではなく、契約と配属の組み合わせ次第で成長度合いが変わる
2) データで見るSESの課題
数字で見ると現実が分かりやすくなります。 業界調査によると、若手SESエンジニアのうち半数以上が「開発以外の作業が多い」と回答しています。
こんなサインが出ていたら要注意です。
- コードレビューの機会が月1回もない
- 設計や要件定義の会議に参加できない
- 作業の9割がテストや監視に偏っている
3) よくある悩みパターン
SESでつまずく人の悩みは似ています。
- 現場で放置される:仕事が与えられず、存在感が薄れる
- テストや雑務ばかり:誰でもできる作業しか任されない
- 案件待機が長い:研修や待機で履歴書が空白になる
- 希望とかけ離れた配属:スキルやキャリアの方向性とズレる
開発経験を積めない7つの原因
1) 現場で放置される
外部委託という立場から距離を置かれ、タスクが回ってこない。話しかけても「あとで」と先延ばし。会議に呼ばれず、情報も落ちてこない。 この状態は“学びと実績がゼロのまま時間だけが過ぎる”のが最大の問題です。 放置はさらなる放置を招き、信頼や評価に影響します。早い段階で小さなうちに手を打つことが大切です。
状況をつかむために、次の観点でチェックします。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 最初の一歩 |
|---|---|---|---|
| 参加機会 | 定例/レトロ/レビューに招集されない | 情報不足 | 会議体の一覧と招待可否を確認依頼 |
| タスク供給 | Jira/Backlogのアサインが0件 | 可視の貢献がない | 「自分から小タスク提案」メモを提出 |
| 連絡経路 | 質問先が不明、返答が遅い | 詰まりが連鎖 | 質問用チャネル・SPOCを合意 |
行動の順番を決めることで、すぐに実行へ移せます。
- まずは10分で片付く“雑だけど価値がある小タスク”(ログ整理、軽微なドキュメント更新)を自分で見つけて提案。
- 次に質問先・承認者・レビュー担当を一枚にまとめ、合意を取る。
- 一週間の最後に“やったこと・詰まり・次週”を3行で共有。
2) 単純作業やテストばかり任される
テストや資料作成は重要ですが、「ITエンジニアとしての開発経験」として残りにくいのが致命的。テスト要員に固定化されると、次の現場でも同じ役割を割り当てられがちです。
“同じ作業”から“価値の高い作業”へ少しずつ引き上げます。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 引き上げの一手 |
|---|---|---|---|
| 作業の粒度 | 手順通りの実行のみ | 学習が浅い | テスト観点/境界値の追記を提案 |
| 道具の使い方 | 手動操作ばかり | 作業時間が増加 | スクリプト/CIで半自動化 |
| 関与の幅 | 結果報告のみ | 背景理解が乏しい | 欠陥の再現手順+原因仮説まで記載 |
3) 案件待機が長期化する
配属が決まらず、社内で数週間〜数か月の待機。履歴書には年数だけが増え、“中身のない経歴”になりがちです。焦りは禁物ですが、何もしないのはもっと危険。
待機期間を“実績づくり期間”に変換しましょう。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 変換アイデア |
|---|---|---|---|
| 空白の増加 | 1〜3か月の未稼働 | 不利な見え方 | 個人アプリMVP→デプロイ→URLを履歴書に |
| 自信の低下 | 手が止まる | 応募が遅れる | OSSのgood first issue×3で即実績 |
| 市場感の欠如 | 求人を見ていない | ミスマッチ増 | 週1で5件だけ求人比較(開発比率/レビュー/自動化) |
- 待機の最初の2週間は“1プロダクト完成”に全振り(規模は小さくてもOK)。
- 以降はOSS×小PRと技術ブログで「見える証拠」を増やす。
- 30/60/90日で面談→軌道修正のリズムを作る。
4) 設計・要件定義の経験を積ませてもらえない
コードは書けるのに、“なぜそう設計したのか”を語れない——ここで頭打ちになります。上流を丸ごと任せてもらえなくても、入口は作れます。
レビュー同席や議事録から、上流に触れる接点を増やします。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 入口の作り方 |
|---|---|---|---|
| 会議不参加 | 要件/設計MTGの招待がない | 背景理解が浅い | 議事録担当を申し出る |
| 設計資料 | 読む機会がない | 点の実装に偏る | 図1枚(コンポーネント/シーケンス)を自作 |
| テスト観点 | 指示待ち | 品質議論に入れない | 自分で観点/データ/境界値を案出し |
- 「議事録+設計図1枚」を毎週積むだけで、説明力が上がり、上流の席に呼ばれやすくなります。
- 小さな仕様変更の影響範囲メモを作り、レビューに載せるのも効果的。
5) 業務範囲が限定されすぎている
DBだけ、監視だけ、オペレーションだけ——横のスキルが育たず、キャリアの可搬性が下がります。 全体像が見えないと、意思決定も学びづらい。
“隣の工程に1歩だけ踏み出す”戦略で範囲を広げます。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 横展開の一歩 |
|---|---|---|---|
| 担当固定 | DB運用のみ | 視野が狭い | ETL/マイグレーションの小タスクを巻き取る |
| 道具の偏り | 同じ手順のみ | 応用が効かない | IaC/CIの“最小設定”を自作 |
| 可搬性 | 現場依存が強い | 転用困難 | 設計意図の言語化を習慣にする |
- 「今日は隣の1タスク」を合言葉に、週1で範囲外タスクを小さく拾う。
- それを“再現手順+学び1行”で記録→可搬性が上がります。
6) 現場の教育・フォロー体制が整っていない
質問先が曖昧、レビューがない、OJTが機能していない。独学だけでは遠回りです。外部の伴走や仕組み化で補えます。
“レビューの仕組み”と“質問の場”を先に作ります。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 補う方法 |
|---|---|---|---|
| レビュー不在 | PRが流れる | 品質が安定しない | 小PR運用とテンプレ導入 |
| 質問迷子 | 誰に聞くか不明 | 手戻り増 | SPOC(一次窓口)を明確化 |
| 学習の拡散 | 教材が散らばる | 定着しない | 週1の振り返り30分を固定 |
- PRは小さく・早く・一日一回。レビューは来やすく、品質は上がります。
- 社外コミュニティ/メンターで週1レビューを確保すると、驚くほど進みます。
7) スキルミスマッチによるアサイン
希望言語や領域と違う配属が続くと、努力が成果に直結しません。 スキルシートが古い、希望が曖昧、成果の言語化不足が原因になりがち。
“可視化・言語化・交渉”の順でズレを縮めます。
| 項目 | サイン | 短期影響 | 修正のコツ |
|---|---|---|---|
| スキルシート | 更新が止まっている | 誤配属の温床 | 直近3か月の実績を箇条書き追加 |
| 希望の曖昧さ | 「できれば◯◯」 | 伝わらない | やりたい/避けたい/条件/時期を一文化 |
| 成果の見せ方 | 抽象的な説明 | 説得力が弱い | 課題→打ち手→数値の三点セットで記載 |
- 上司への相談は事実→希望→代案→期限の順。
- 社外に目を向け、求人票で“どの経験が刺さるか”を逆算すると、シートが磨かれます。
7つの原因を一望して、優先順位を決める
一気に全部は難しくても、“今日の一歩”は必ず選べます。
| 項目 | 深刻度の目安 | 最初の対処 | 1週間のゴール |
|---|---|---|---|
| 放置 | 会議・タスクが0 | 小タスク提案+SPOC合意 | 会議1つ参加・タスク1件着手 |
| 単純作業固定 | 手動/指示待ち | 自動化or観点追記 | 改善PRを1本出す |
| 待機長期化 | 1〜3か月 | MVP完成→公開 | ポートフォリオURL化 |
| 上流経験不足 | 会議不参加 | 議事録担当→図1枚 | 設計レビューで発言1回 |
| 範囲が狭い | 単一工程のみ | 隣の小タスク拾い | 横の成果を1件可視化 |
| 教育不全 | レビュー不在 | 小PR運用+週1振り返り | レビュー履歴が1本 |
| ミスマッチ | 希望と配属ズレ | シート刷新→面談 | 配属調整の可否判定 |
止まらなければ、必ず前に進めます。 できることから、ひとつずつ。明日のあなたは、今日より確実に前に進んでいます。
ケーススタディ:開発経験が積めなかった実例
実際の体験談からは、多くの学びを得られます。
- Aさん(24歳) 案件待機が半年以上続き、スキルを発揮する場がなかった。 → 学習ログを毎日残し、ポートフォリオを作成してようやく次の現場へ。
- Bさん(28歳) テスト工程ばかりで開発に関われず、3年が経過。 → 単純作業を自動化するスクリプトを提案し、結合テスト設計に携わる機会を得た。
- Cさん(30歳) 希望のWebバックエンドではなく運用に配属。 → スキルシートを更新し、上司と面談して転属。加えて副業開発で実績を積み、自社開発企業への転職に成功。
失敗も成功も次に活かせる材料。 「何もしないこと」だけが一番危険です。
開発経験を積むための対処法
「開発ができないまま時間が過ぎてしまうのではないか…」と感じているITエンジニアにとって、今すぐ取れる選択肢を知ることは安心につながります。 ここでは、開発経験を積むための具体的な行動を6つ紹介します。どれも難しいことではなく、小さな一歩から始められる工夫です。
1) 副業でシステム開発を経験する
副業は“収入”と“経験”を同時に得られる効率の良い選択肢です。 SESの現場で開発に関われなくても、副業案件を通してコードを書き、設計を学ぶことができます。
副業の入り口としては、クラウドソーシングでの小規模案件が取り組みやすいです。まずは「バグ修正」や「機能追加」といった短期間の仕事を選びましょう。最初は月に数万円程度の収入でも、積み上げれば実績になります。
| 種類 | 内容 | 単価目安 | 学べるスキル |
|---|---|---|---|
| クラウドソーシング | 小規模改修・バグ修正 | 3〜10万円/件 | 基本実装・顧客とのやりとり |
| 受託開発チーム | 数週間単位のプロジェクト | 10〜40万円/案件 | 設計・Git運用・レビュー |
| 知人紹介案件 | 社内ツール整備など | 応相談 | 要件定義・改善提案 |
ポイントは「実績を必ずポートフォリオにまとめる」こと。 受けた案件はGitHubやポートフォリオサイトに整理し、転職活動で活用しましょう。
2) オープンソースや個人開発に参加する
“自分の作品を公開すること”は強力な武器になります。 GitHubにコードを公開したり、個人アプリをストアにリリースすれば、採用担当に「実際に動く成果」を見せられます。
OSS(オープンソースソフトウェア)への参加もおすすめです。特に「good first issue」と呼ばれる初心者向けタスクは、ハードルが低く挑戦しやすいです。
- 最初は小さなバグ修正やドキュメント改善から始める
- コードだけでなく、READMEに「何を解決したか」を書き残す
- 毎週少しずつ更新して“継続力”を見せる
このような積み重ねは、履歴書や面接での「証拠」として大きな説得力を持ちます。
3) 上司に案件変更を依頼する
社内で調整できるなら、それが最短距離です。 「開発に関われる案件に移りたい」という希望を、感情ではなく事実に基づいて伝えましょう。
- 現状:作業比率が監視80%、開発0%
- 希望:開発タスクを一定割合経験したい
- 提案:小規模開発タスクから徐々に関わらせてほしい
このように、具体的な数値や事例を添えて話すと説得力が増します。 理解ある上司であれば調整してくれる可能性が高いです。もし対応してもらえない場合は、その会社での将来性を見直すきっかけにもなります。
4) メンターや学習コミュニティを活用する
学習は一人でやるより、伴走者と一緒の方が効率が上がります。 質問できる環境やレビューを受けられる場があると、理解のスピードも精度も高まります。
- 週1回のオンラインレビューを受ける
- 学習コミュニティで成果を共有する
- ミニ課題を出してもらい、短期で取り組む
例えば「毎週1つ小さなアプリを完成させ、コードレビューを受ける」といったペースを作るだけでも、半年後には大きな力になります。
5) 自社開発企業へ転職する
本格的に開発経験を積みたいなら、環境を変えるのが最も確実です。 自社サービスを持つ企業では、要件定義から運用まで一貫して携われるため、SESにはない成長機会があります。
| 観点 | SES現場 | 自社開発 |
|---|---|---|
| 仕事内容 | 配属先の指示で断片的な作業 | 要件〜実装〜運用まで通しで関与 |
| スキル蓄積 | 案件ごとにリセットされがち | 長期的に積み上げ可能 |
| 成長スピード | 現場によって差が大きい | 一貫した経験で速い |
転職はハードルが高く感じるかもしれませんが、長期的なキャリアを考えるなら避けて通れない選択肢です。
6) 資格を取得してスキルを証明する
資格は「実力を客観的に見せる」手段です。 現場で開発に関われなくても、資格があれば「基礎力がある」と証明できます。
特におすすめは以下の流れです。
- 基本情報技術者試験で基礎を固める
- 応用情報技術者で広く知識をカバー
- PythonやJavaなど言語系資格で実装力をアピール
資格そのものよりも、資格取得を通じて学んだことを実務でどう活かすかが重要です。履歴書や面接で「学んだ知識をこう応用したい」と話せるよう準備しておきましょう。
自己発信で差をつけるスキルアップ策
ただ学んでいるだけでは、誰にも伝わりません。発信することで評価が加速します。
自己発信の手段はいくつかあります。
- GitHub:毎週のコミットで「継続的にコードを書いている」と示す
- 技術ブログ:学んだ内容を記事化し、検索から読まれるようにする
- SNS:成果を共有し、同じ志を持つ人とのつながりを作る
| チャネル | 効果 | 続け方 |
|---|---|---|
| GitHub | 実装力の可視化 | 小さな更新を毎週積み上げる |
| ブログ | 知識の整理+検索流入 | 「1つの学び=1記事」で短く続ける |
| SNS | 横のつながり、機会の創出 | 宣伝よりも「共有」の姿勢で発信 |
発信を続けることで、キャリアの選択肢が自然と広がります。
キャリア形成の長期的視点
1) 5年後のキャリアシミュレーション
「今の半年」は「5年後のキャリア」に直結します。
| 観点 | 開発経験あり(5年後) | 開発経験なし(5年後) |
|---|---|---|
| 役割 | 設計・レビューを担う中心人物 | 運用や監視業務に偏る |
| 年収レンジ | 中〜上位レンジ | 伸びが緩やか、頭打ち |
| 選択肢 | 自社開発、社内SE、リードエンジニアなど幅広い | 案件の選択肢が狭まる |
| 転職力 | 複数社で即戦力として歓迎される | 採用で不利になりやすい |
違いは数年単位でじわじわ現れますが、気づいたときには大きな差になります。
2) 30代で差がつく分岐点
30代前半までに積んだ経験の厚みが、その後の交渉力を決めます。
- 設計やレビューの経験があるか
- 長期プロジェクトでの関与経験があるか
- 改善を数値(性能向上・コスト削減など)で語れるか
この3つを30代前半までに押さえている人は、市場価値が大きく違ってきます。
3) 放置すると待っている末路
「今のままでも大丈夫」だと思っていると、数年後に厳しい現実に直面します。
- 単純作業ばかりで評価されない
- 待機期間が増えて経歴に空白ができる
- モチベーションが下がり転職も難しくなる
90日間のリカバリー計画
- 1か月目:ポートフォリオ1本を完成させる
- 2か月目:副業やOSSで小さな実績を積む
- 3か月目:転職面談や社内異動交渉で市場に触れる
小さな一歩を止めないことが、キャリアを守る唯一の方法です。
SESからのキャリアチェンジ戦略
いまの環境で伸びづらいなら、“伸びやすい土台”へ移るのが合理的です。 ここでは3つの方向性を丁寧に比較し、移行のステップまで具体化します。焦らず、でも確実に前進しましょう。
1) 自社開発・受託開発企業への転職
継続的にコードと設計へ触れ、プロダクト思考を育てたいなら最有力。 自社開発は同じサービスを継続改善でき、受託開発は案件ごとに新技術へアクセスしやすいのが特徴です。
| 観点 | 自社開発 | 受託開発 |
|---|---|---|
| 経験の深さ | 1つのドメインを掘り下げやすい | 複数ドメインに触れて幅が出る |
| レビュー文化 | 仕組み化されやすい(定例/規約) | チーム差があるが多様な流儀を吸収 |
| 担当範囲 | 要件→設計→実装→運用まで通しやすい | 工程は案件と役割に依存 |
| 成長の方向 | 深さ・再現性・品質改善 | 速いキャッチアップ・適応力 |
| 向く人 | 腰を据えて磨き込みたい | 変化が好き・学習速度が速い |
応募前のチェックリスト
入社後ギャップを防ぐため、次の点を言語化して確認します。
- 開発サイクル(スプリント長、計画/レトロの運用)
- コードレビューとテスト自動化の実態(必須/任意、カバレッジ)
- バグ・技術負債への向き合い方(バックログ/定例)
- チーム構成(レビュー役・メンター・QAの有無)
- リモート可否、出社頻度、稼働時間の中央値
面接で語る“3本柱”
面接は“再現性の証明”がカギです。 1. 課題:現場の具体的なボトルネック 2. 打ち手:設計/実装/運用の改善策 3. 結果:数値(性能・障害・工数・コスト)で効果を説明
2) 社内SE・DX推進のポジション
“業務理解×IT”で社内の仕組みを変えたい人に向いています。 課題発見から要件化、内製ツール開発、ベンダー調整まで幅広く関与できます。
| 領域 | 主な仕事 | 伸びる力 | 相性が良い人 |
|---|---|---|---|
| 社内SE(内製) | 業務アプリ開発・運用、権限管理 | 要件整理/UI/運用設計 | 現場課題を解くのが好き |
| DX推進 | 業務可視化、RPA/自動化、データ活用 | 合意形成/PoC/分析 | 対人調整が得意 |
| ベンダー管理 | 選定・契約・品質/納期管理 | 交渉/評価/リスク管理 | 外部折衝に強い |
はじめ方のミニ手順
最初の1件で“成果の型”を作ると早いです。
- 現場ヒアリング(時間がかかる/属人化している作業を特定)
- As-Is/To-Beの簡易図解を作成 3. 小規模PoC(RPA・iPaaS・ローコードでまず動かす)
- 効果測定(処理時間/手戻り/エラー率)を数値化
- 展開計画(運用フロー・権限・ログ・教育)
3) ITコンサル・フリーランス独立
“外側から課題解決”で価値を出す選択。裁量は大きいが自己管理が必須です。
| 働き方 | 収益性 | 必要資質 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| コンサル(正社員) | 中〜高 | 構造化/提案/合意形成 | ドメイン学習と信頼獲得が鍵 |
| フリーランス | 中〜高(変動) | 営業/品質/納期管理 | 複数顧客・支払サイト・資金繰り |
リスクを抑える準備
リスク管理は“見える化”と“仕組み化”から。
- 実績の一枚資料(背景/役割/打ち手/効果)×5本
- 契約テンプレ(秘密保持・成果物の権利・検収条件・支払サイト)
- 税務と社会保険の体制(青色申告/インボイス/積立)
転職サポートサービスの選び方
サービスは“相性”で結果が変わります。複数タイプを使い分けると成功率が上がります。 固有名詞は扱わず、タイプごとの強みと活かし方を整理します。
| タイプ | 強み | 弱み | 合う人 |
|---|---|---|---|
| IT特化型 | 技術理解が深い、非公開求人が多い | 対象が偏る場合あり | 技術軸を磨きたい |
| 総合型 | 求人数が広い、比較検討しやすい | 技術深掘りは弱め | 選択肢を広げたい |
| 自社開発特化型 | SES除外でミスマッチ減 | 枠が限られる | プロダクト志向が強い |
| ブティック系 | 少数精鋭で密な伴走 | 地域/領域が狭い | 深い支援を求める |
| 直応募/スカウト | 一次情報が速い、企業理解が進む | 対策は自力 | 気になる企業へ直接当たりたい |
自分の“軸”を先に言語化する
軸が明確だと提案の質が一気に上がります。
- やりたい/避けたい領域(例:Webバックエンド/運用主体は避けたい)
- 使いたい/学びたい技術(例:Go+GCP、IaC)
- 就労条件(年収レンジ、リモート、出社頻度、稼働時間の中央値)
- いつまでに内定が欲しいか(目標時期)
ミックス運用で“抜け”を減らす
IT特化+総合+直応募の3経路で情報の非対称性を縮小。 同一企業でも経路ごとに見える条件が違うため、比較が精密になります。
相性の判定ポイント(初回2週間)
連絡速度と理解の深さは重要なシグナルです。
- 返信が72時間以内、週次で提案/フォローが来るか
- 求人要約が“コピペ”でなく、現場の運用/働き方まで触れているか
- あなたのNG条件(保守比率、出社頻度など)を反映できているか
メッセージ例(短文)
要件を短く、でも具体的に。 「自社開発のバックエンド中心。設計レビューあり、テスト自動化が回っている環境を希望。保守比率80%以上はNG。リモートは週3以上、年収は〇〇〜〇〇万円、3か月以内の内定を目標にしています。」
FAQ:よくある質問
迷いは自然なこと。事前に疑問を解消できれば、行動は軽くなります。
1) 副業は会社にバレますか?
就業規則と税の扱いでリスクは下げられます。 会社の副業規定、業務外/私物端末の徹底、住民税の取り扱いの理解がポイント。守るべき線を明確にしておけば安心です。
2) 未経験スタック(例:Go/Rust)へ切り替えたいです。
“小さく作る→公開する→語る”の順番が最短。 個人アプリ1本+OSSの小PR3本を目安に、READMEで設計意図と学びを簡潔に整理。技術ブログで補足すれば説得力が増します。
3) どの資格から始めればいいですか?
基礎→応用→言語系の三段ロケットが無理なく進みます。 基礎を押さえ、広く俯瞰し、最後に得意言語で実装力を可視化。資格名だけでなく「実務でどう活かすか」を話せる準備が大切です。
4) 案件待機中にやるべきことは?
“履歴書に残る”活動を最優先。
- ポートフォリオ1本を完成(起動手順・スクショ・技術選定理由を明記)
- OSSで小PRを3件(ドキュメントでもOK)
- 週20時間の学習計画(設計/テスト/クラウドの基礎)
5) 30代からでも間に合いますか?
十分に間に合います。 設計・レビュー・改善のエピソードを数値で語れるよう準備し、自社開発/受託/社内SEの3方向で比較検討。経験の“厚み”が交渉力に直結します。
6) 年収交渉はどう切り出すと良いですか?
根拠(市場水準/直近成果/役割拡張)+レンジで柔らかく。 「直近で◯◯改善(◯%向上)。入社後は◯◯領域までカバー予定。レンジは〇〇〜〇〇万円を想定しています」と伝えると角が立ちません。
7) 書類選考が通りません…
余白を削って“何ができる人か”を即伝える構成へ。
- 職務要約は5行以内に圧縮(得意領域/成果/強み)
- 成果は数値で(◯%/◯件/◯ms/◯万円)
- 技術は「使った→どの課題を解決した」で記述
- GitHub/ポートフォリオを冒頭にリンク
完璧な計画より、今日の小さな一歩。 メールを1通送る、PRを1件出す、記事を1本書く——その積み重ねが、数か月後のあなたを大きく変えます。焦らず、でも止まらず。あなたのキャリアは、いま、この瞬間から前向きに動かせます。
法務・労務観点の補足
法律と社内ルールを理解しておくことは、キャリアの“安全装置”です。 難しく考えすぎなくて大丈夫。まずは「契約書」「就業規則」「業務委託・副業規定」を落ち着いて読み、気になる点をメモしましょう。
契約・労務の要点(迷ったらここから)
| 項目 | 要点 | 確認ポイント | アクション例 |
|---|---|---|---|
| 契約形態(準委任/派遣/請負) | 指揮命令・責任範囲が変わる | 指揮命令系統/成果物の責任 | 契約書の該当条項を付箋でマーキング |
| 秘密保持(NDA) | 情報の取扱いと罰則 | 持ち出し禁止・公開可否 | GitHub/ブログ投稿前にチェック |
| 知的財産(著作権/利用許諾) | 成果物の権利帰属 | 副業/個人開発との線引き | 雇用外時間・私物機材で分離運用 |
| 就業時間/残業 | 36協定/深夜・休日割増 | 打刻/工数提出ルール | 勤怠を“毎日”確定(後回しはNG) |
| ハラスメント相談 | 相談窓口と記録の扱い | 社内/社外窓口の有無 | 日時・発言・対応を時系列で記録 |
| 副業規定 | 可否/申請/競業避止 | 住民税/情報持ち出し | 業務外・私物端末・データ分離を徹底 |
| 在宅勤務ルール | 端末/ログ/画面共有 | 私物利用の可否 | 画面ロック・家族同席NGを習慣化 |
もし“労務インシデント”が起きたら
| 状況 | 初動 | 避けるべきこと | 次の一歩 |
|---|---|---|---|
| 未払い/過重労働 | 証拠(勤怠・指示チャット)を確保 | 感情的なやりとり | 上長/人事へ事実ベースで報告 |
| ハラスメント | 日時・場所・発言を記録 | 録音の可否が不明な収録 | 相談窓口(社内/社外)へ連絡 |
| 情報事故の疑い | 速やかに報告・隔離 | 自己判断の隠蔽 | 情報システム部門の指示に従う |
まとめ:SESで開発経験を積めるキャリアを選ぼう
成長できる環境に身を置く。これがいちばんの近道です。 とはいえ、環境は一夜で変わりません。だからこそ、“今日できる小さな前進”を重ねていきましょう。
ポイント3つ
- 原因を言語化:放置・単純作業・待機・上流不足・範囲の狭さ・教育不在・ミスマッチ
- 打ち手を分散:副業・OSS/個人開発・案件変更交渉・メンター活用・自社開発転職・資格
- 見える化を継続:GitHub・ポートフォリオ・数値で語れる改善事例
よくある目的別の“次の一手”
| 目的 | やること | 期間の目安 | 評価される観点 |
|---|---|---|---|
| 今の現場で役割を広げたい | 小さな自動化/改善を1本 | 2〜4週間 | 効果(◯%短縮/減) |
| 実務経験を補強したい | 副業の小改修×2件 | 1〜2か月 | 納期/品質/やり取り |
| 転職で選択肢を増やしたい | ポートフォリオ1本+改善事例3本 | 1〜2か月 | 再現性のある実績 |
| 自社開発へ移りたい | 設計/レビュー経験の可視化 | 1か月 | 設計意図/テスト観点 |
焦らなくて大丈夫。 ただし、止まらないこと。数週間単位の積み上げが、数年後の景色を変えます。
今日からできるアクションプラン
計画はシンプルでいい。動ける計画が、良い計画です。 以下の順に進めれば、迷いにくくなります。
1) 最初の24時間
まず“動き出す”体験を。小さく、速く。
- GitHubに新規リポジトリを作成(READMEに「課題/解決/技術/起動手順」を記入)
- 過去学習の成果物を1つ整えて、スクリーンショットを追加
- 気になる求人を3社だけブックマーク(条件:開発比率/レビュー/自動化)
- 次の1週間の学習時間をカレンダーに固定(毎日30〜60分)
2) 7日プラン
一週間で“見える成果”を1つ。
- OSSのgood first issueを1件クローズ
- 個人アプリのMVP(最小機能)を完成
- 上司へ案件変更の相談メールを送る(事実→希望→代案→期限の順)
- 技術ブログを1本公開(600〜1200字でOK)
相談メールの短文テンプレ
「現場の作業比率が監視80%・開発0%のため、3か月以内に開発30%以上を目標に小規模開発タスクへ参加したいです。2週間以内に可否をご相談いただけますか。」
3) 30/60/90日ロードマップ
3か月で“語れる実績”を作る。リズムよく進みましょう。
| 期間 | 目標 | 具体アクション | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 30日 | ポートフォリオ1本完成 | MVP→README→デプロイ | URL/スクショ/技術選定理由 |
| 60日 | 実務換算の実績化 | 副業orOSSの成果×3件 | PR/課題→解決/レビュー履歴 |
| 90日 | 市場検証&軌道修正 | 面談(社内/社外)×3 | 改善事例スライド×3本 |
4) 週次ルーティン(習慣化のコツ)
習慣が、実力を連れてきます。
- 月:今週のゴールを1つ決める
- 水:中間レビュー(30分)
- 土:仕上げ→振り返り→翌週のタスク1件だけ決める
アクションのチェックリスト
| 項目 | 基準 | 達成のサイン |
|---|---|---|
| コードの可視化 | 毎週コミット | 緑の草が増えている |
| 学びの定着 | 週2本のメモ/ブログ | 検索からアクセスが発生 |
| 対外接点 | 月3件の応募/面談 | 返信/日程調整が走る |
| 改善の数値化 | 1件につき効果を1つ | ◯%短縮/◯件削減の記録 |
大丈夫。 あなたのキャリアは、今日から動かせます。小さな一歩を重ねれば、迷いは自信に変わります。